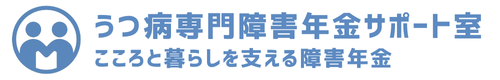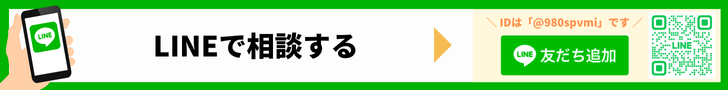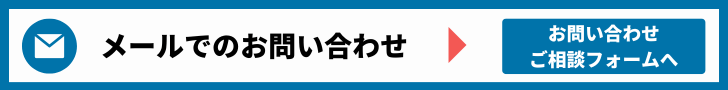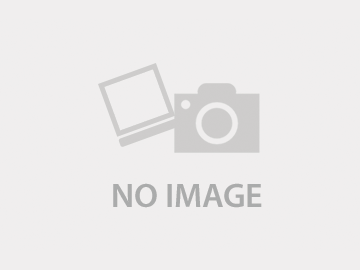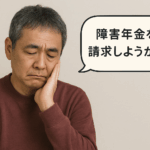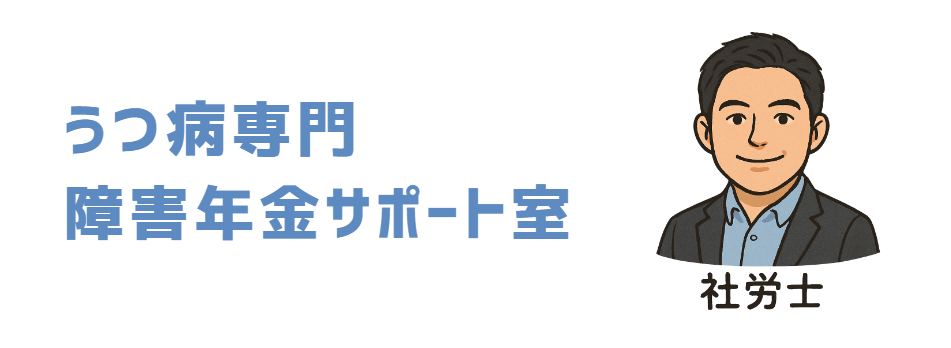パワハラとは
労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)では、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」と定義しています。
また、パワハラ防止法30条の2第3項をうけて定められた「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」では、職場におけるパワハラを、①優越的な関係を背景とした言動であって②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③労働者の就業環境が害されるものであり、上記①~③までの要素をすべて満たすもの、と定義しています。
パワハラの特徴は、同じハラスメントであるセクハラと比較すると、浮き彫りになります。
簡単に言うと、セクハラは「業務に全く必要でない」という性質がありますが、パワハラは「業務の延長線上で不可避的に発生する性質のもの」という違いがあります。
そして、職場で上司が部下に対して注意や指導をすることは、業務の一環として必要なことではあるのですが、それが行き過ぎると、パワハラに該当する恐れがあります。
従って、パワハラは、セクハラと違い、どこまでセーフのゾーンに入る正当な注意・指導なのか、どこからがアウトのゾーンに入ってしまうのかが非常にわかりづらい、という特徴があります。
パワハラの6類型とは
パワハラ指針では、パワハラの代表的な言動の類型として、以下の6つを示しています。
①身体的な攻撃(暴行・脅迫)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・業務の妨害)
⑤過小な要求(業務上の合理性がなく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
上記6類型は、パワハラの代表的・典型的な事例を挙げていますが、当該6類型に列挙されているもののみがパワハラに限定されるわけではなく、これらに該当しなくてもパワハラに該当する場合があるので、その点に注意が必要です。
参考となる判例
参考にしたい判例としては、A保険会社上司事件というものがあります。
これは、上司からの電子メールでの叱責の事案で、メールの内容として「やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います。当サービスセンターにとっても、会社にとっても損失そのものです」という、退職勧奨とも会社にとって不必要な人間とも受け取られるような表現が盛り込まれており、これが被害労働者のみでなく、同じ職場の従業員十数人にも送信されていました。
それとあいまって、「あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか?あなたの仕事なら業務職でも数倍の実績をあげますよ。(中略)これ以上、当SCに迷惑をかけないでください」という、侮辱的な言質と受け止められても仕方ない記載もありました。
これをうけて、当該判例では、「被害労働者の名誉感情をいたずらに毀損するものであることは明らかであり、上記送信目的が正当であった、その表現において許容限度を超え、著しく相当性を欠くものであって、被害労働者に対する不法行為を構成するというべきである」としました。
当該判例は、指導の内容の表現や指導の内容を認識する者の範囲などを考慮して、指導が業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、と判断した例です。
営業職によくあるパターン
職場内で、営業担当者別の営業成績を掲示して、目標金額までの進捗管理を行うと同時に、担当者のモチベーションアップを狙う事は、どの会社での営業部門でもよくありえる事で、それだけで直ちにパワハラに該当するものではありません。
ですが、営業成績を掲示するだけにとどまらず、例えば、ノルマを達成できなかった担当者に奮起してもらう目的で「このままの状態では辞めてもらうしかない」といった内容のメールを、上記事件と同様に営業部門に所属する他の営業社員にも写しで送るような場合や、営業成績表に、最下位の担当者を「今月のビリ」などと記載するなど侮辱するような表現が含まれていた場合はどうなるでしょうか?
これらの場合は、パワハラの定義のうち、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動になるかどうかというのが問題になります。
営業ノルマを達成できない担当者に改善を促すために、メールで激励をすることだけであれば正当な指導といえますが、その激励の内容や手段が相当な範囲を超える場合には、パワハラに該当します。
上記の具体例のように、営業チームに所属する担当者複数人に対してメールを送信することで、他人に見せしめのような形で侮辱的な言葉を用いて叱責することは、名誉棄損や侮辱に該当する可能性もあり、不適切な指導でありパワハラといえるでしょう。
営業ノルマを達成できなかった担当者だけにメールを送る場合でも、「このままの状態では辞めてもらうしかない」とまでいわれれば、担当者に対してもう会社にいられなくなるのではないかと強い不安を抱かせ、強い精神的苦痛を与える言動であり、通常であれば「今月は気持ちを切り替えて頑張ってくれ」程度の叱咤ですむはずです。
これは、パワハラ該当性の判断基準である①~③までの要件をすべて満たしており、やはりパワハラに該当するといえます。
営業成績表の掲示がメンタル面に及ぼす影響
営業成績表の掲示が、個々の労働者のメンタル面に及ぼす影響についても考えてみたいです。
「また今月も最下位だった……」
そんな思いを抱えながら、自分の名前が並んだ成績表を毎朝目にする―これは、当事者にとって非常につらい軽験となります。
営業成績は数字で評価されるため、どうしても順位や差が可視化されがちです。しかし、それを全社員が見える場所に貼り出すという行為は、成績の上がらない社員の方には「頑張っても報われない」「自分には価値がない」と感じさせ、心に深い傷を残すことが十分に想定されます。
特に真面目で責任感の強い方ほど、自分を責め続け、やがて自信を喪失し、抑うつ状態に陥ってしまうことも十分にありえます。
「職場に行くのが怖い」「胃が痛くなる」といった体調不良を訴えるケースも少なくありません。
「成績を公表して競争意識を高めたい」という会社側の意図はわかるのですが、それが社員の尊厳を傷つけてしまえば、逆効果です。職場は人を追い詰める場所であってはなりません。
成績の可視化は、上述のように場合によってはパワハラとみなされる可能性もあるのですが、大切なのは、数字の先に心を持った“人”がいるということを忘れないことです。
総合的な考察
職場内に営業担当者別の営業成績を掲示することのみでも、経営者や営業部という会社内の1組織における営業部長などの各営業担当者に優越する地位の者の判断によって行われたものであり、パワハラ指針の①優越的な関係を背景とした言動、という要素を満たすものと考えられます。
そして、それら営業ノルマや営業目標が過大な場合は、それがパワハラを引き起こす要因ともなりえます。
過大な営業目標が営業部全体に与えられることによって、上司である営業部長や課長にも相当なプレッシャーがかかり、それが原因で、担当者に対しても人格を否定するような名誉棄損や侮辱につながるのです。
そこでパワハラ指針の中では、経営者が行う望ましい取り組みの内容として、パワハラの原因や背景となる要因を解消するため、適正な業務目標の設定や適正な業務体制の整備、業務の効率化による過剰な長時間労働の是正などを通じて、労働者に過度に肉体的・精神的負荷を強いる職場環境を改善することがあげられています。
単に営業部全体にの担当者別営業成績を掲示することは、すぐにパワハラに該当するとは言えませんが、上述したように、経営者が設定した営業成績や営業ノルマが過大なことが、パワハラを引き起こす遠因となる場合が十分に考えられます。
そして、そのパワハラ行為が職場環境を悪化させ、各営業担当者のメンタル面に悪影響を及ぼすことになります。結果として、職場全体の生産性低下にもつながるのです。
ですから、パワハラ防止を営業部長や課長個人の責任とするのではなく、パワハラ行為の背景に経営者の掲げた数値目標やノルマが影響を与えていないか、背景も含めて総合的に精査する必要があるのです。
メンタル不調から、休職になってしまった場合の所得補償の制度については、こちらの記事からご確認下さい。
休職期間満了による退職に至ってしまった場合の所得補償の制度については、こちらの記事からご確認下さい。
退職後の生活を支える制度である障害年金が受給できるかどうかの要件は、こちらの記事から確認できます。
◆トップページ・運営者プロフィールはこちらから