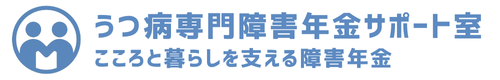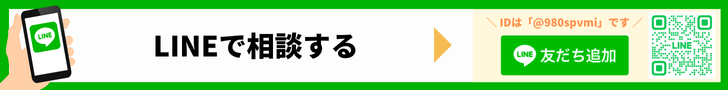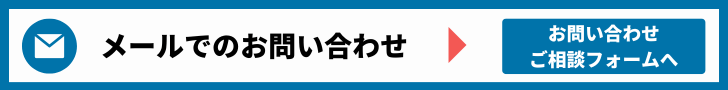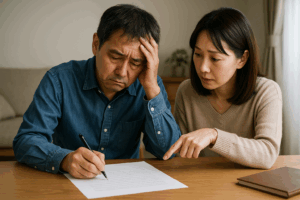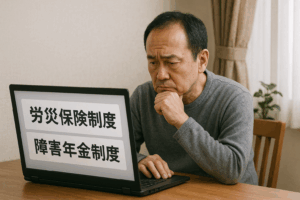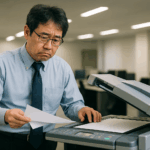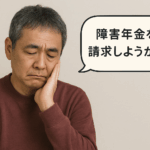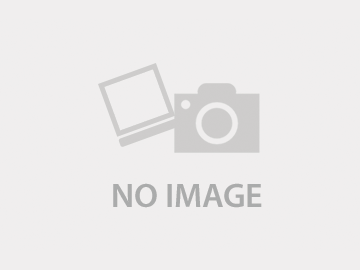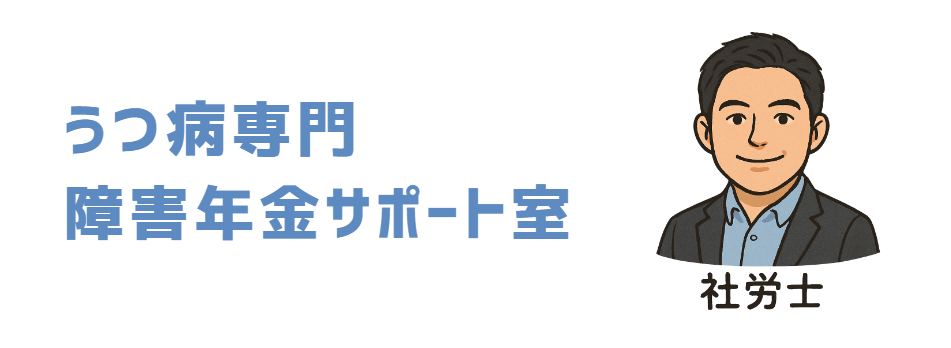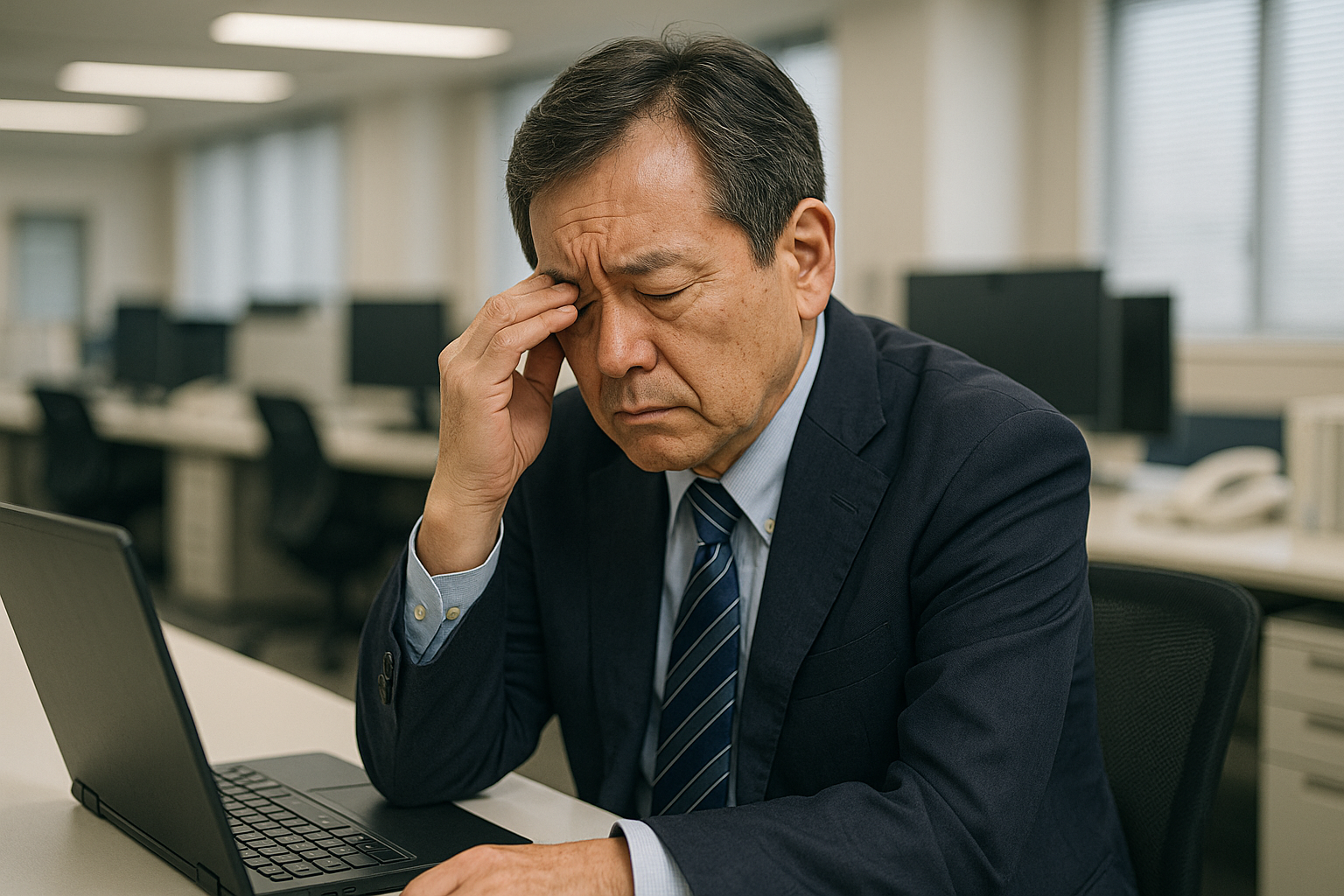
メンタル不調で休職したものの、ようやく復職できた——それはご家族にとっても大きな一歩だったはずです。
しかし復職後、会社がまともな仕事を与えず、ただ出社だけを求める、あるいは形だけの業務しか与えないという事態が起きていませんか?
それは明らかに「干し」と呼ばれる不当な処遇であり、会社が暗に当該社員に間接的に退職をせまっている事を想起させることから、メンタル不調の再発リスクを大きく高める非常に危険な状況にあります。
なぜ「干し」は不当なのか
会社には、その雇用する労働者に対して、生命や身体等の安全を確保しつつ労働することが出来るよう、必要な配慮をしなければならない「安全配慮義務」があり、この中には、当然、「心身の健康」も含まれます。
また、上記にと共に、昨今の労働者のメンタル不調による休職の増加を踏まえて、「職場復帰支援義務」も課されるようになりました。
これは通常、「リワーク支援」といわれるもので、これが近年、会社側でも重要な取り組みになっており、厚生労働省のほうでも、「心の健康問題により休業した労働者の復帰支援の手引き」を公表しています。
メンタル不調で休職した社員が復職する際には、上記手引きに基づき、その状態に配慮した適切な業務を与え、段階的に職場復帰を支援する義務があります。
この段階的に職場復帰することをリハビリ出社ともいいますが、こういった措置を踏まずに、仕事を与えないことは、上記義務に明確に違反するものであり、精神的な圧力をかける「職場いじめ」の一種と評価されることさえありえるのです。
リハビリ勤務とは?
リハビリ勤務は法律上の制度ではなく、その捉え方も様々ですが、通常休職から復職をするにあたっては、復職した当初から、所定労働時間の労働時間をフルに行うのではなく、段階的な勤務であるリハビリ勤務やトライアル出社等の仕組みを導入する会社も多くなっています。
朝の定時の出社を繰り返す通勤訓練や、1日の所定労働時間よりも短い勤務をし、勤務時間を段階的に増やしていくという具合に、フルタイムの勤務を目指して社員に徐々に負荷をかけていくというやり方です。
また、休職期間中に、医療機関などが実施するリワークプログラムに参加し、その結果を復職の際の判断材料とする場合もあります。
リワークプログラムは、生活リズムや作業能力の回復、発症要因の分析、対人関係能力の回復などが目的で、復職可能かの判断材料として、プログラム通りに出席できているかどうかや、自身のメンヘル疾患と向き合い、自分のストレス対処の仕方を分析し、復職した場合のストレスに対し対応可能なまでに回復しているかが重要であるとされました(東京電力パワーグリッド事件)。
復職する際の会社のとるべき対応
復職できるか否かの判断するにあたっては、原則としては、従来の業務の通常程度に行える健康状態に回復したことを要します。
しかし現実的には、すぐに従来の業務にすぐに復帰することはメンヘル不調の再発リスクもあるため、その社員の能力や会社の実情に照らし配置できる可能性がある他の業務を考慮する必要があります(片山組事件など)。
上記判例から、会社はメンヘル疾患を患った社員の復職に際しては、まずその社員の能力や会社の実情から配置されうる現実的な他の業務による復職や、回復傾向にある社員については軽減業務による復職も考慮することが求められます。
また、厚労省が発表した上記手引きでも「円滑な職場復帰のためにも、職場復帰後の労働負荷を軽減し、段階的に元へ戻す等の配慮は重要な対策となる」としており、軽減な業務をへた職場復帰が望ましいとされています。
ですので、復職後に仕事を与えないことは労契法に定める「安全義務配慮」とはなりません。
一見すると「負担をかけないようにしている」ようにも思えますが、人間は“必要とされていない”と感じることで大きなストレスを抱えるように精神構造上できています。
仕事を与えられずに、やりがいも社会的役割も奪われると、ご本人の自尊心は大きく損なわれます。
これは“配慮”ではなく、“放置”であり、メンタル不調を再発させるリスクが極めて高い危険な状況といえます。
実際の事例と出来る対処例
復職後3ヶ月間、別室での勤務を命じられ、そこで社史の編纂業務だけを命じられた40代男性がいました。
当初は我慢しながら勤務を続けていたものの、日を追うごとに職場に居場所を感じらなくなり、再びメンタル不調が再発し、不眠と不安に襲われる毎日となり、メンタル面が削られていき結果的に退職。
こうした会社の処遇は、パワハラの6類型
のうちの、「人間関係からの切り離し」と「過少な要求」の二つにあてはまる可能性が十分にあり、その場合はパワハラにも該当します。
メンヘル不調から復職したばかりとはいえ、社史の編纂という本業とは関係のない業務を与えることや、それを他の社員が就労する職場とは離れた別室で行わせるという事は、本人の労働意欲や能力に反し、行き過ぎた業務命令でありパワハラ行為であるといえます。
こうした状況でできる対処方法は、
-
自分を責めないようにすること
-
状況を記録(日時・仕事内容・上司とのやりとり)するようこと
-
精神科医や外部相談窓口(都道府県労働局・法テラスなど)へ相談すること
-
必要に応じて労働問題に強い弁護士・社労士と連携をとること
があげられます。
特に重要なのが「状況の記録」で、復職後に置かれている“仕事を与えられない”という状況が、メンタル面に大きな負荷を与えることになります。
その観点から、その状況の記録によるパワハラ該当の証拠収集が、将来的に労災申請や法的措置に発展する可能性もあります。その際、重要になるのが「客観的な記録」です。
なぜ記録が必要なのか?
-
言った言わない問題を防げる
-
状況の継続性・悪質性を証明できる
-
医師・弁護士・労働局雇用均等室に相談する際の材料になる
記録すべき内容
-
出社・退社の時間と実際の業務内容(何もない日も“何もなかった”と記録)
-
上司との会話や指示(直接の言葉、メールなど)
-
その時感じた心身の状態(不安・疲労・焦燥感など)
記録の形式は自分でできる方法で大丈夫
-
スマホの日記アプリやメモ機能
-
紙のノート
-
Excelなどの表形式
重要なのは*「主観と客観の両方を混ぜて、継続的につけること」*です。
まとめ:「干されている」状況を変えるために今できること
復職後にもかかわらず、会社がまともな仕事を与えず放置するのは、労働者としての尊厳を奪う行為であり、明確な不当な扱いです。そのまま我慢し続ければ、メンタル不調の再発につながりかねません。
具体的には、以下のような段階的な行動を取ることで、状況を少しずつ動かすことが可能となります。
ステップ①:記録をつける(※前述の記録内容を参照)
-
まずは自分の置かれている状況を可視化することが第一歩です。
-
精神的ダメージは見えにくいからこそ、日々の出来事や心身の状態を記録することが重要となります。
ステップ②:会社に対して「業務内容に関する相談・要望」を申し出る
-
勇気のいることですが、「このままでは仕事に復帰した実感が持てず、心身にも悪影響が出ている」と、具体的に伝えることが効果的です。
-
「処遇についての要望書」等を書面やメールで残す形で「適切な業務への配置や職場復帰支援を求める」と伝えることで、記録にもなります。
ステップ③:産業医や人事労務、社内相談窓口に相談
-
「復職支援プランが不十分である」との訴えは、産業医の判断を仰ぐ正当な理由になります。
-
特に産業医のような客観的な第三者が介入すると、会社としても放置できなくなる事は多くあります。
ステップ④:必要で応じて社外の支援機関へ相談
-
地元の労働基準監督署(精神的負荷の労災対応など)
-
労働局の総合労働相談コーナー(無料)
-
労働問題に強い弁護士(初回無料相談を活用)
最後に、心療内科・精神科への継続的な通院も重要です。
「干されていること自体がストレスになっている」と主治医に伝えてください。主治医が診断書などを通じて、会社に対して職場配慮の必要性を明示することも可能となります。
重要なのは、メンタル面がギリギリになるまで我慢しない事です。
その為には、日々の証拠収集と共に、退職した場合の国の所得補償制度についても調べておくことです。
※退職後の所得補償制度については、こちらの記事からご確認下さい。
退職に当たっては、雇用保険の離職票での退職理由を会社都合による退職としてください。これについては、会社側も比較的スムーズに認める傾向がありますし、そうすることですぐに失業給付を受け取る事が出来ます。
また、メンタル不調が再発してしまった場合は、将来的な暮らしの補償の事も踏まえ、主治医と障害年金の申請もご相談ください。
失業給付は長くて1年程度で切れてしまいますが、障害年金はその症状が続く限り支給され続けます。
※障害年金が受給できるかの要件は、こちらの記事からご確認下さい。
◆トップページ・運営者プロフィールはこちらから