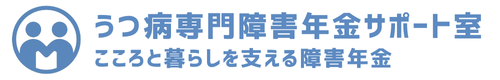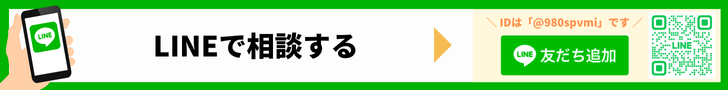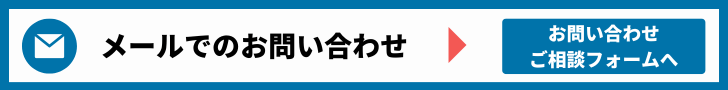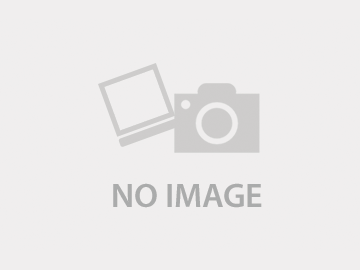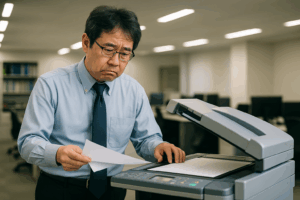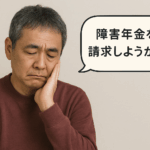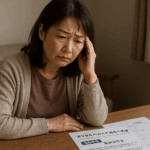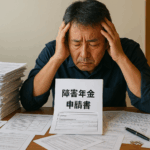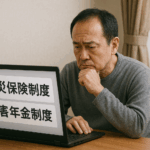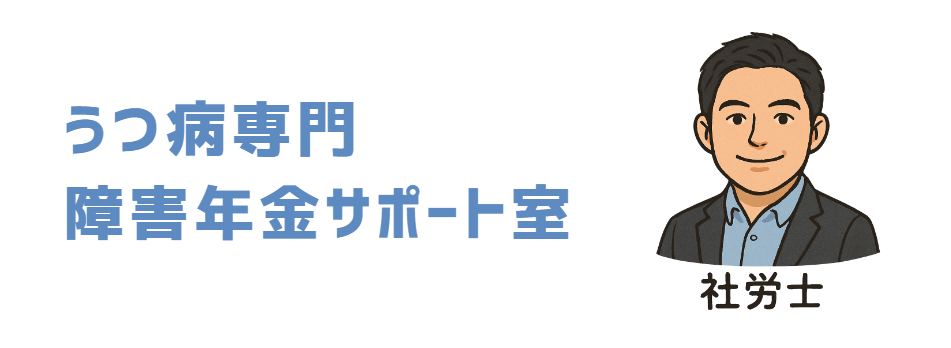ジョブ型人事制度とは
最近、大企業を中心に浸透してきた人事管理制度に「ジョブ型雇用」と「ジョブ型人事制度」があります。
ジョブ型雇用については、だいぶ世間でも知られてきていますので、ここではその詳細にまでは触れませんが、要は、会社内における個々のポジションや職務内容をもとに人材を活用する仕組みのことで、ある職務に空きが出た場合に、在籍する社員から最適な人材をその職務につかせるか、もしくは社外から採用する等をして個々の職ごとに人材をあてがう仕組みです。
一方で、ジョブ型人事制度とは、ジョブ型雇用の浸透に伴って、以前からある「職務等級制度」の呼び方を変えただけのことがほとんどです。
職務等級制度とは、職務の内容や難易度、責任度合いの職務の価値を評価してグレードに分類・格付けし、その職務に対応する賃金テーブルを準備する制度のことで、いわゆる成果主義賃金制度の一つと解されます。
従来の職能資格制度と異なるのは、勤続年数・学歴・年齢などの属人的要素を考慮しないで、職務内容の価値をもとに格付けが決められ、等級と職務内容とを関連付けます。
ジョブ型人事制度のデメリット
ジョブ型人事制度では、その会社内に存在するジョブを明確にして(職務記述書)、かつそのジョブに価値づけをしなければならいため、評価の作業が膨大になります。
また、同一のジョブ等級の属する者は、年齢や経歴にとらわれず、その等級に対応する賃金レンジの中でその貢献度に応じて処遇されるため、不公平感は少なくなる半面、ジョブによって給与等が変わりえるため、社員がそのジョブを遂行できなかった場合に柔軟な配置換えなどがしにくくなるという点があります。
この点につき、参考なる判例として、エーシーニールセン・コーポレーション事件では、「労働契約の内容として、成果主義による基本給の降給が定められていても(中略)降給が許容されるのは、就業規則等による労働契約に、降給が規定されているだけでなく、降給が決定される過程に合理性があること、その過程が従業員に告知されてその言い分を聞くなどの公正な手続きが存在することが必要」と判事しています。
つまり、就業規則等に評価に伴う賃金の減額の可能性を示唆するような包括的な定めがあったとしても、評価結果による降給が会社の人事権の濫用にあたる場合は、それは許されません。
ジョブ型人事制度の有効性
ジョブ型人事制度の運用に当たっては、ジョブ内容の変更に伴い処遇を決定することが雇用契約の内容になっていなければなりませんし、ジョブごとの賃金額の設定であるレンジが、ジョブ内容との比較で妥当といえることも必要です。また、当該人事制度では、ジョブ内容の変更に伴って給与が下がる可能性もあります。その為、会社側としてはメリットのある制度かもしれませんが、社員に対しては、ジョブ内容の変更によって賃金減額になるという労働条件の不利益変更の問題になりえます。
そこで、上記エーシーニールセン・コーポレーション事件では、当該制度の有効性の判断として、
・降給は、各等級の給与範囲が相対的に高いものに厳しく、低いものに有利な仕組みになっているが、降給者がいる一方で、多くの者が昇給する仕組みになっていることという事実を認めることができる。各期ごとの目標設定と目標ごとの評価という仕組み自体に合理性を認めることができる。
・上司の評価の結果は従業員に告知され、従業員が意見を述べることができ、従業員の自己評価も会社の人事部門に報告されるという仕組みには、一定の公平さが担保されているということができる。以上から、会社が新人事制度により導入した成果主義による降給の仕組みには、合理性と公平さを認めることが出来るという結論となる。
としています。
付け加えると、評価基準が明確で、2人以上の者により評価が行われるなどで恣意的な判断がは序できる仕組みであったり、評価に対する異議申し立て制度により公平さが担保されている、これらが社員に周知されている、そして実際の査定及び昇給・降給が当該仕組みに沿って適切に行われていることが必要であるとしました。
ここまでジョブ型人事制度を厳格に運用して、はじめてその人事制度が有効と認められるわけです。
降給(降格)の有効性
ジョブ型人事制度において、社員があたえられたジョブを遂行できない(遂行できる能力がない)と評価される場合には、会社はジョブの変更(配置転換)や職位の降格を検討せざるを得ません。
しかし、実務上はジョブ等級の引き下げに伴い賃金減額を生ずるものであることから、ジョブ等級の変更だけでなく、ジョブ等級の変更に伴う賃金減額についても、就業規則上で規定しておくか、社員の個別的同意を得ることが必要です。賃金の減額は、労働契約の最も重要な要素を変更するものであるため、賃金の降給を伴うジョブ等級の降格を経営者の裁量にゆだねることはできないのです。
具体的には、会社は就業規則において、降格とジョブ等級の変動の連動だけでなく、ジョブ等級の変動と賃金減額の変動についても明確に定めて社員に周知しておく必要があります(その期の評価がX評価以下の場合は基本給を・・・円下げる、という具合です)。
実際の事例からの示唆
医薬品を製造・販売する外資系会社の日本法人に雇用された労働者が、営業成績が低いことから、営業職係長から営業事務職への配転命令により、給与等級が2段階下がった結果、給与がほぼ半減した事案(日本ガイダント仙台営業所事件)があります。
上記事案は、当該降格配転が配転命令の側面と等級の降格の側面の両面があることから、前者については基本的に会社の人事裁量の範囲内にあるとしつつ、後者については大幅な賃金減額するような場合は客観的合理性がない限り無効と解すべきであるという一般論をたてました。
そのうえで、具体的な考慮要素として、
・営業成績が低いことに対する当該労働者への帰責性
・降格配転命令の動機及び目的
・経営者の業務上の必要性
・会社における降格の運用状況(従前の賃金が約半分となるような同程度の降格の有無)
を例示・検討し、降格が無効となった場合には配転も無効となり、本件降格配転全体を無効とすべきであると判事しています。
賃金減額を伴う配転命令については、通常の配転よりも業務上の必要性も含めてより厳しく判断しているわけです。
総合的な考察
ジョブ型人事制度では上記のように、業務上に必要性も含め、ジョブ変更が認められるか否かという点で紛争になる可能性が高く、それが賃金の大幅な減額がともなうほど、より厳しく判断されます。
ですので会社側としては、その様な場合でも、いきなり全額を減額せずに6ケ月~1年程度かけて徐々に減額していくなどの措置をとることがベターでしょう。
また、労働者としては、配転降格に対して同意はせずに、当該配転降格に異議のある旨の通知を内容証明郵便による郵送し、異議を唱えるべきと考えます(異議を唱えないと、当該配転降格に対して黙示の同意をおこなったと判断されるリスクがあるため)。
ただし、異議を唱えたからといって、実際の就労までも拒否すべきではありません。就労を拒否すれば、それが業務命令違反にあたるとして、経営者から懲戒処分や解雇等のさらなる不利益処分が科される可能性が高く、その処分が有効だと判断される恐れもあるからです。
ですので、現実的には、就労自体は配転となった業務に従事しつつ、当該配転降格の無効を訴えていくというのがとりうる手段だと考えます。
◆トップページ・運営者プロフィールはこちらから