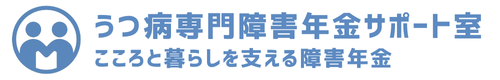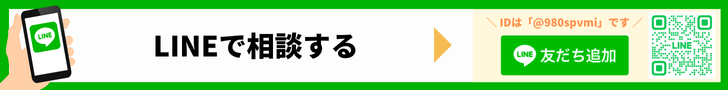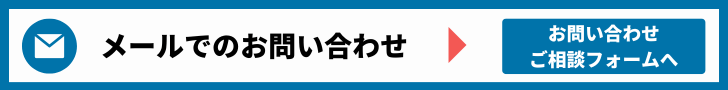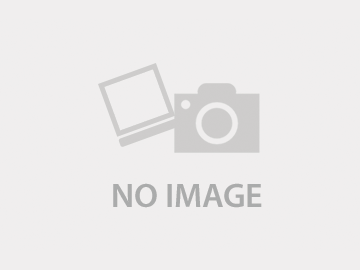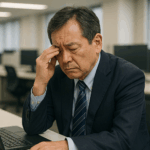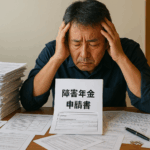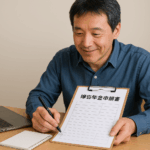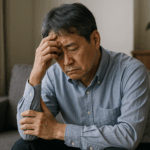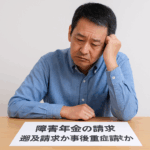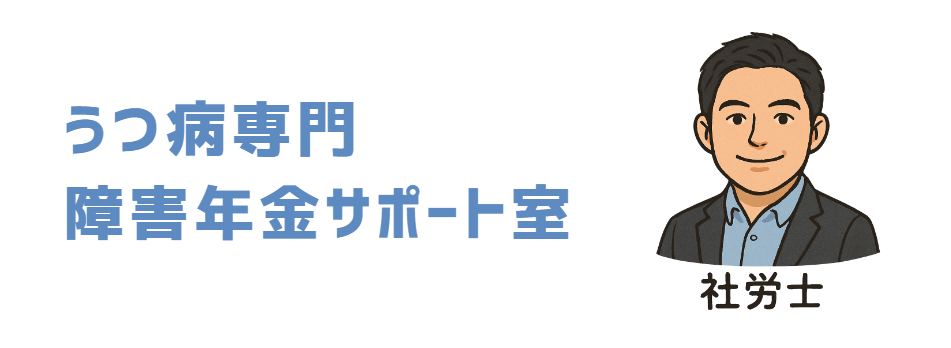労働時間とは
労働時間の一般的な定義として、過去の判例では「労働者が使用者の指揮命令以下にある時間」と解されています。難しい表現をしていますが、要は所定労働時間内に通常の仕事をしていれば、それは労働時間に当たるわけですが、例えば、昼休み中に職場にいて来客対応や電話番をするようないわゆる手待ち時間も、具体的な業務はしていないにしても、作業の遂行のために場所的に拘束されているという意味では労働時間に当たるとされています。
上記の指揮命令下にある時間ですが、これは上司が明確に部下に対して指示や命令を与えた場合だけでなく、包括的な指示や、黙示の指示・命令を行った場合も含みます。
サービス残業問題を考えるにあたっては、この黙示の指示・命令があったかなかったかが問題となるケースが多いのです。
黙示の指示・命令と残業許可制
黙示の指示・命令とは、簡単に言うと「黙認」のことです。労働者が勝手に残業していたとしても、それを黙認していれば、「残業しなさい」と命じたと同じことになります。
具体的な例をとって、このことを考えています。
京都銀行事件では、始業時間は午前8時35分だが男性行員のほとんどが8時過ぎまでには出社し、8時15分までには金庫の扉を開けてキャビネットを出すなどの業務の準備をしていた、ということでした。
この事件において、裁判所は、午前8時15分から35分までの金庫の開封などを行う業務は経営者側が黙認しているのだから早出残業であり、残業代を支払う必要があると判断しました。
男性行員のほとんどが午前8時15分から仕事をしており、上司もそれを知っていて止めることはなかったわけですから、これは黙認していたことになり、そうした以上それは業務命令しているのと同様で、当該時間は労働時間として賃金が発生すると判断されたのです。
このような事を起こさないために、経営者側としては、会社の許可なく残業を行っている社員を黙認しないことが大事だということで、「残業許可制」を採っている会社が多いと思います。
所定労働時間内に仕事を終わられることを原則としつつ、それでもどうしても残業が必要になった場合に限って、なせ残業が必要なのか、どの程度の残業時間が必要なのかを明確にして許可申請をさせて、上司が当該業務を行うのに適正な労働時間を過不足なく許可してから残業させることにするのです。
ただ実際の運用にあたっては、上司が部署全体の業務の進捗状況や部下の仕事量を把握したうえで、残業を許可するかどうかの判断をしなけれなならず、上司に相当な負担がかかります。
ですから実態としては、形式的に上司の事前許可を必要とする就業規則の規定があるだけであったり、残業の必要性を精査しないで単に残業を禁止する指示を出すことが多いようです。
サービス残業と国の対応(参考)
平成不況の経済情勢や雇用失業情勢の中で、企業においては、残業の過少申告などにより割増賃金を支払わないですませるサービス残業が相当広くみられるようにみられるようになりました。
さらに、長時間労働による過労死・過労自殺への世論の批判が一層たかまったことを契機に、厚労省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定し、公表しました。
同ガイドラインでは、経営者には労働時間を適正に把握する責任があるとしたうえで、主な要点として、①経営者は労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すべきであること、②その原則的な方法としては、経営者らが自ら現認することによる確認と、タイムカード、ICカード、パソコンの記録等の客観的な記録を基礎としての確認・記録とがあり、やむをえず自己申告制で労働時間を把握する場合には、
・自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても、自己申告制の適正な運用等について十分な説明を行う
・自己申告により把握した労働時間と入退場記録やパソコンの使用時間との間に著しい乖離がある場合にをは実態を調査し、労働時間の所要を補正すべき
・経営者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等、適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならず、また36協定の延長限度時間数をこえて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者において慣習的に行われていないかを確認すべき
としています。
さらにふみこんで、厚労省による長時間労働にかかる労基法違反の防止徹底し、会社による自主的な改善を促すため、社会的に影響の大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業場で繰り返している場合、都道府県労働局長が経営者層に対して全社的に早期是正について指導するとともに、その事実を公表する方針が打ち立てられました。いわゆる「ブラック企業への是正指導と企業名公表」と報道された施策です。
上記のような国の施策は、サービス残業の取り締まりというだけでなく、労働者の長時間労働による肉体的・精神的両面での健康被害を抑制しようとする目的があります。
残業許可制の有効性(判例から)
上記の国の施策を受けて、多くの会社で残業許可制が広まったわけですが、残業許可制があるからと言って、許可をうけていない残業がすぐに労働時間ではないと否定されるわけではありません。それは、許可の有無という形式的な基準ではなく、残業を行う業務上の必要性の有無や経営者の管理の厳格さにより判断されるのです。
具体的な判例として、「クロスインデックス事件」があります。
この判例では、午後7時以降の残業を行う場合は、経営者の許可を得る必要がある「残業許可制度」がある会社で、許可を得ていない残業代を求めたケースで、判例は、
「被告労働者が会社に対して所定労働時間内にその業務を終了させることが困難な業務量の業務を行わせ、会社の時間外労働(残業)が常態化していたことからすると、本件係争時間のうち会社が被告労働者の業務を行っていたと認められる時間については、残業許可制に従い、被告労働者が事前に残業を申請し、会社の代表者がこれを許可したか否かに関わらず、少なくとも会社の黙示の指示に基づき就業し、その指揮命令下におかれていたと認めるのが相当であり、割増賃金支払いの対象となる労働時間に当たるというべきである」
と判事しました。
要するに、残業するにあたり残業許可制により、事前に残業の許可を得ることが就業規則などにより規定されていたとしても、業務の実態から黙示の業務命令・指示がある場合は、許可をえていないとしても当該残業は労働時間に該当する判断したわけです。
総合的の考察
上記のことから、形式的に上司の事前許可を必要とする就業規則の規定があるだけであったり、単に残業を禁止する指示を出すだけで、当該残業が労働時間とならないことにはなりません。
つまり、実質的に残業を解消する措置がとられておらず、恒常的に残業が行われる状況が改善されないまま、残業を形式的に禁止する規定をおいたり、残業を禁止する指示・命令をしたりするだけの場合は、当該残業は労働時間となり、会社には割増賃金の支払い義務が発生します。
残業許可制を有効なものとするためには、当該許可制が運用上も、残業が毎日個別具体的に必要は否かを適正に判断したうえで、時間外勤務命令書などによって命じられ、かつ勤務後に当該残業を労働者本人が実時間として上記書面に記載し、それを上司が確認することにより残業時間を把握するというような厳格な運用が必要、とされています。
もっとも、上記のように厳格に運用していた場合であっても、残業が、当該残業に要する時間、指示された業務の期限、他の社員への引継ぎなどの代替措置の有無などを総合的に勘案し、残業禁止命令が不合理である場合、つまり残業しなければ処理しきれない業務を指示されているような場合というのがよくあるパターンではないかと思いますし、この様なケースでも、会社には労働者に対して割増賃金を支払い義務が発生する可能性が高いです。
※当オフィスでは、初回無料相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。