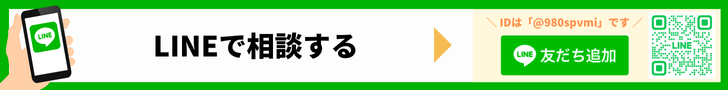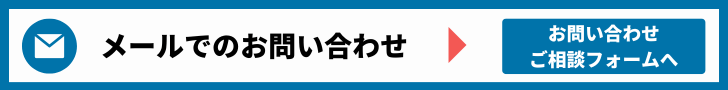懲戒処分の定義と法的根拠
懲戒処分とは、経営者が、社員の企業秩序違反行為(服務規律違反、業務命令違反、信頼関係の破綻、会社の信用棄損等)に対して加える制裁罰の事で、その種類には、懲戒解雇、諭旨解雇、降職・降格、出勤停止、減給、けん責、戒告、訓告などがあります。
ですが、そもそも経営者は、どのような公的根拠に基づいて上記のような懲戒処分を成しえるのでしょうか?
本来、経営者と労働者は対等な労働契約の当事者であるところ、なぜ経営者が通常の人事裁量権を超えた制裁罰としての懲戒処分を行えることが出来るのか、その法的根拠が問題となります。
そこで判例では、「労働者は、労働契約を締結して雇用されることによって、使用者に対して労務提供義務を負うとともに、企業秩序を遵守すべき義務を負い、使用者は、広く企業秩序を維持し、もって企業の円滑な運営を図るために、その雇用する労働者の企業秩序違反行為を理由として、当該労働者に対し、一種の制裁罰である懲戒を課することが出来る」(関西電力事件)としつつ、
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種類及び事由を定めておくことを要する。そして、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知される手続きが採られていることを要するというべきである」(フジ興産事件)として、懲戒権の行使には就業規則における懲戒規定の定めとその周知が必要としています。
※懲戒処分に要する根拠規定となる就業規則上の懲戒事由や手段の列挙は、限定列挙と解されています。
懲戒処分に関する法律と取り決めなど
労契法15条は「使用者が労働者を懲戒することが出来る場合において、当該懲戒が、当該懲戒にかかる労働者の行為の性質及び態様その他の事情を照らして、客観的に合理的理由をかき、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効とする」と規定しています。
具体的には、懲戒処分は、実質的に周知された合理的な内容の懲戒処分の根拠規定の存在を前提として、①懲戒事由該当性②処分の相当性(懲戒権濫用ではない事)③手続きの相当性(適正手続)の3つの要件を満たして有効なものとなります。
上記3要件に加えて、懲戒処分は企業秩序違反行為に対する制裁罰であるため、適正手続が必要であるだけでなく、よい広範囲の罪刑法手主義類似の諸原則が適用され、これらの諸原則に違反していないかの確認をうけます。諸原則は下記のとおりです。
・罪刑法定主義の原則:懲戒の種類・程度が就業規則上明記されている
・不遡及の原則:懲戒処分の根拠規定が設けられる以前のの行為に対しては、さかのぼって懲戒処分の対象とす ることはでき
・一事不再理の原則:一度懲戒処分の対象となった事由について2回以上の懲戒処分を行うことはできない
・平等取り扱いの原則:同種の非違行為には、同一種類で同程度の処分をかす
・適正手続きの原則:就業規則上、賞罰委員会の討議・決議を要する場合や労働協約上協議などを要する場合には、それらの手続きを適正に行う。それらの規定がない場合でも、最低、本人に弁明の機会を与える
無断欠勤と法的問題
通常、無断欠勤や出勤不良、遅刻・早退などの職場離脱があった場合には、職場秩序を乱す行為として、就業規則の懲戒事由に該当することとなる可能性は高いです。
ただ、一般的には、いきなり懲戒解雇とはならず、一度注意を行ったうえで、それでも改善がない場合に比較的軽い処分の懲戒を行い、さらに改善がない場合に雇用関係を解消する懲戒処分を行うというステップを経ることが必要です。
また、会社に行きたくてもいけない状態に陥るのに、労働者のメンタルヘルス不調が原因であるケースが多く、この場合は、懲戒処分にも注意が必要とされます。
具体的には、職場で嫌がらせをうけていると信じて無断欠勤を約40日続けた労働者に諭旨解雇の懲戒処分をした事案のおいて、経営者は精神科医による健康診断を実施するなどして上で、その診断結果に応じて、必要な場合は治療をすすめたうえで休職などの処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり、かかる対応をせずに諭旨退職の懲戒処分の措置をしたことがは、メンタルの不調を抱える労働者に対する経営者の対応としては適切なものとはいえず、この様な事情の下では、労働者の欠勤は就業規則上の懲戒事由にある「無断欠勤」にあたらず、諭旨解雇処分は無効であると判示した事案があります(日本ヒューレット・パッカード事件)。
その他の判例
栴壇学園事件
大学教員の3月13日から4月13日までの連続する無断欠勤について、就業規則の懲戒解雇の事由には該当するとしつつ、当該欠勤は春休み中で授業もなく、大学の業務に支障をきたさなかった等の事情を考慮して、無断欠勤のみで懲戒解雇処分は権利濫用であると判示しました。
・日本郵便事件
就業規則上で約20日以上の無届欠勤の処分について諭旨解雇または懲戒解雇とする旨の懲戒規定が定められていたところ、26日間連続した無断欠勤を行ったことを理由に、諭旨解雇処分とした事案です。これに対し労働者が退職届の提出を拒み続けたことから行った懲戒解雇を有効と判示しました。
労契法15条との関係
無断欠勤が懲戒解雇処分に当たるかどうか、労契法に定める「社会通念上相当の相当性」の観点から考えてみたいと思います。
無断欠勤日数が何日に達したら、当該処分が社会通念上相当とされるかどうかは、明確な基準があるわけではなく、過去の判例では、日数のみで判断するのではなく、その他さまざまな事情を考慮しています。
具体的には、
・欠勤の回数・期間・程度・正当な理由の有無
・業務への支障の有無・程度
・経営者(上司含む)からの注意・指導・教育の状況、経営者の管理体制
・本人の改善の見込み、反省の度合い
・本人の過去の非行歴、勤務成績
・同様の先例があるかないか、同様の事例に対する処分との均衡
といった様々な事情を総合的に考慮し当該処分の有効性を判断しています。
また、「客観的・合理的な理由」があるかどうかの側面からみると、無断欠勤の内容について「届け出はあるが正当な理由のない欠勤」も含むのかという問題もあり、これに関しては就業規則上「届け出があった場合でも、その理由が正当でないときは、無断欠勤として扱う」という根拠規定を就業規則に定めるケースが多いと想定されます。
総合的な考察
上記にあげた判例などから、何日程度無断欠勤したら解雇が有効とされるのかは一概にいう事はできません。
また、昨今では労働者が無断欠勤に至るのに、職場のパワハラやいじめによるメンタルヘルス不調が原因であるケースが増加している傾向があり、それは正当な理由として主張しづらいという性質をもっているためです。
こういった場合は、会社側の職場環境の管理体制の不備が問題であり、上記判例にように一旦解雇処分となったとしても解雇無効と判断される可能性が高いです。
ですから、メンタルヘルス不調による無断欠勤の場合は、医師よる診断書などを会社に提出し、そこに至ってしまった経緯を正直に伝えるのがベターでしょう。
会社側としても、それを受けたうえで、自社の職場環境の改善などの措置を取りつつ、当該労働者にも改善・指導を図るべきで、そういった措置を行わずに解雇してしまうと、当該解雇は無効と判断されると思われます。
※当オフィスでは、初回無料相談を行っています。お気軽にご相談ください。