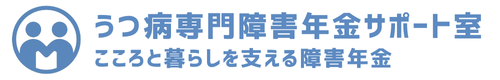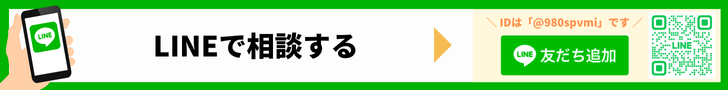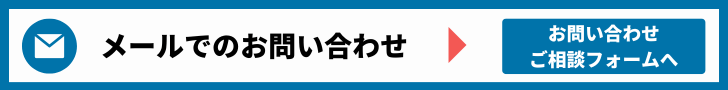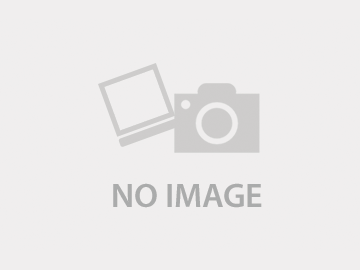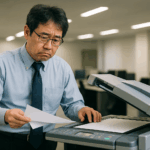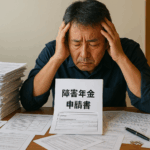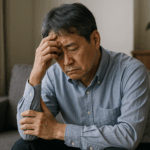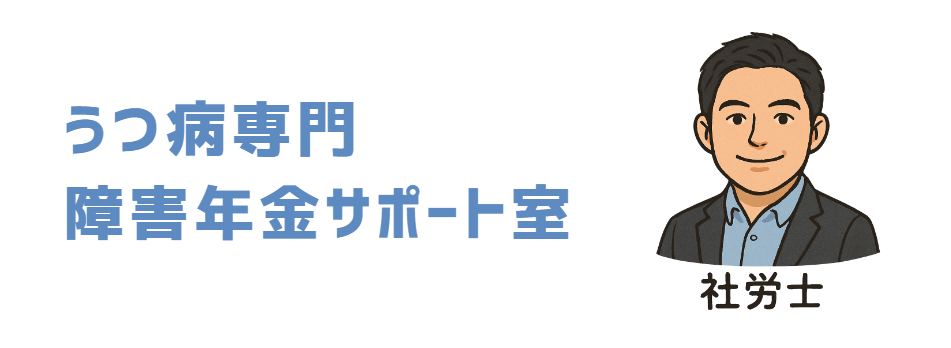休職制度とは
労働者が業務外による傷病によって長期の療養を要する場合に、多くの会社ではこれを労務不能とみなして、直ちに解雇などの処置をするのではなく、長期の休職期間を設けています。
休職制度は多くの企業で採用されていますが、実は労働関係法令上に規定はなく、休職制度を設けるのは企業側の任意になります。ですから、本来であれば傷病が治癒されず長期の療養が必要な場合は、労働契約が解除(解雇)されてしまうところ、それではあまりに酷であろうという事から、これを一定期間関猶予するもので「解雇猶予措置」としての意義をもっています。
休職からの職場復帰は、関係者の意向が複雑に絡み合う
よくあるケースとして、労働者の主治医は復職可能とする診断書を出しているものの、会社とその産業医が復職は難しい考えることがあげられます。
ここで問題となるのが、休職事由の消滅や復職の要件となる私傷病の「治癒」をどうとらえるかです。
原則として、治癒とは従来の業務にを通常とおり行うことが出来る健康状態までに回復したことを意味すると解されています。そして治癒していると認められれば復職という事になり、この判断は最終的には経営者がするのですが、だからといって経営者の恣意的な判断は認められません。
そこで、「治癒」しているかどうかを客観的に判断する必要があり、この判断にあたっては労働者が提出した主治医の診断書が有力な判断材料の一つと考えられます。
ただそれのみによるものでもなく、実際には私傷病の内容や症状、治癒の経過、従前の業務内容やその負担の程度、会社の産業医や人事労務担当者の意見やその他の事情などを総合的に勘案して、客観的に判断することになります。
厚労省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」でも、「主治医による診断書の内容は、病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、それはただちにその職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとは限らないことにも留意するべきである。また、労働者や家族の希望が含まれている場合もある」と記載されています。
従ってこの手引きでは、それと同時に産業医の役割として「主治医による職場復帰可能の判断が、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限らないため(主治医は必ずしも職場の状況を詳しく把握しているわけではない)、主治医の判断と職場ので必要とされる業務遂行能力の内容などについて、産業医等の精査を経て採るべき対応を判断すること」としています。
要はこの手引きでは、職場の状況を把握し、かつ医学的見地を有する産業医の意見を十分に斟酌し、その復職の可否を判断するように求めているのです。
裁判所も判断しかねている?
過去の判例上も、私傷病が精神疾患の場合に、傷病が治癒したかそうでないかの判断について、労働者側の主治医と会社側の産業医の見解が対立し、その判断が難しくなることがあります。
その場合のいい具体例として、NHK名古屋放送局事件では、いわゆるリハビリ出勤制度を活用して、その期間中の労働者の業務状況を踏まえて傷病が治癒しているかいないかを判断することにより、労働者の現状や職場の実態などに即した合理的な判断ができると考えられるとし、リハビリ出勤は復職の可否の判断において有用としています。
そのうえで、当該労働者のリハビリ出勤中における職場内での言動や、診察中の言動といった具体的な出来事に基づき、復職不可と判断した産業医等の意見を採用し、リハビリ出勤実施後も当該労働者の精神疾患は治癒していないと判断しました。
復職を求める際に注意すべき事項
上記のように休職からの職場復帰に当たっては、様々な関係者が存在し、それぞれの意見を総合的に勘案し客観的に判断する必要があります。
そのうえで、近年では休職した労働者が、職場復帰可能となったことについて経営者に示さなけれなならないとするのが一般的になってきました。これは、経営者による恣意的な解雇や自然退職を防止する意味合いもあると想定されます。
職場復帰の立証の準備として、私傷病休職の場合には、原則として従前の業務に復帰可能なことが、復職の要件となる「休職事由の消滅」にあたります。
ですので、主治医には、できるだけ具体的に①どの職場で②いつから復帰可能であること③その理由、を診断書に明記してもらうのがよいです。そのうえで、経営者との面談でも、働く意思も意欲もあることをきちんと伝えることが重要です。
復職可能であることを立証する証拠としては、やはり主治医による復職可能の診断書の提出が一般的です。
しかし、主治医の診断書は「復職したい」という労働者の希望により作成されおり信頼性がないとして、主治医の復職可能の診断書が提出されていたにもかかわらず、産業医等の意見を重視して休職期間満了による退職を有効とした判例もあります(幻冬社コミックス事件)。
そこで、主治医の診断書のみに頼らず、自身の健康状態を客観的に立証できるリワークプログラムへの参加や、日々の生活状況を記録して健康状態を示す証拠とすることもしたほうがいでしょう。そのことによって、主治医医の診断書の信頼性を裏付けることにもなります。
結論
復職可能とは、基本的には従前の職務を通常程度行うことが出来る状態にある場合をさしますが、仮にそれに至らない場合でも、相当の期間内に作業遂行能力が通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込める場合も含むとする判例があります(総企画設計事件)。
ですので、当初の労働契約において職種が限定されていなかった場合は、従前の業務が出来なくても復職が認められる場合はあります。仮に職種が限定されている場合であっても、他の軽易な業務への配置可能性に言及した判例もあり、また仮に従前の職務が遂行できる程度の回復していなかったとしても、復帰当初は軽易な業務に就かせて徐々に通常業務に服させることも考慮すべきとした判例もあります(エール・フランス事件)。
従いまして、休職期間満了時近くなっても、客観的に従前の業務が遂行可能な状態まで回復していなかったとしても、又は経営者から、従前の業務の遂行が不可能と判断されてしまった場合でも、諦めることなく軽減された業務での復職は可能であることを主張していくべきでしょう。
※当オフィスでは、初回無料相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。