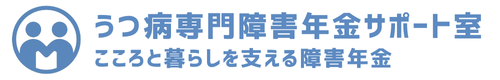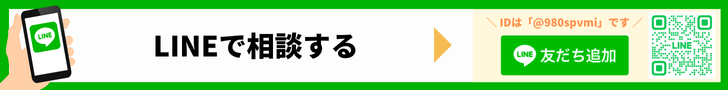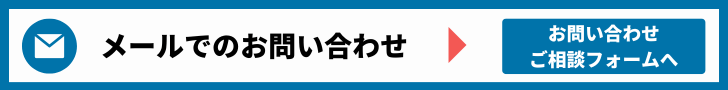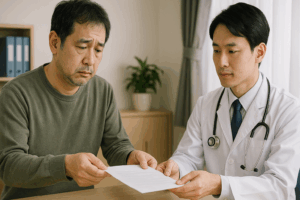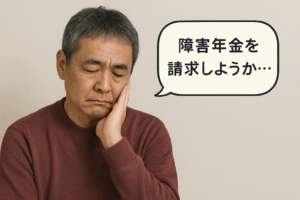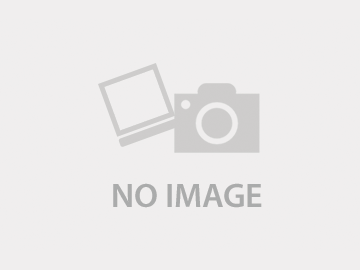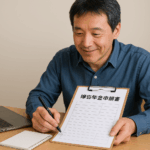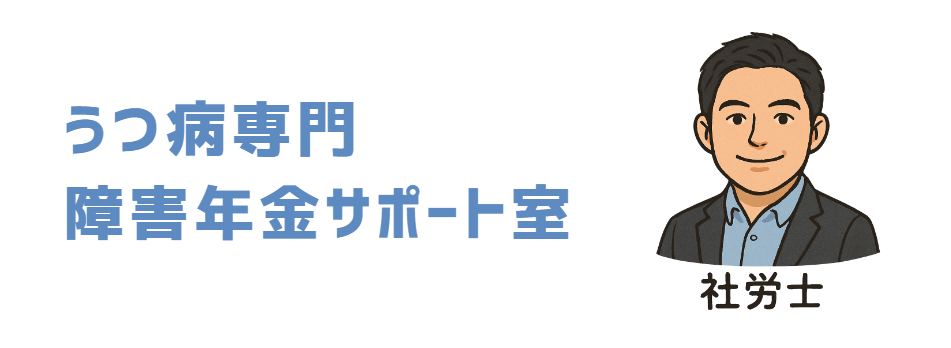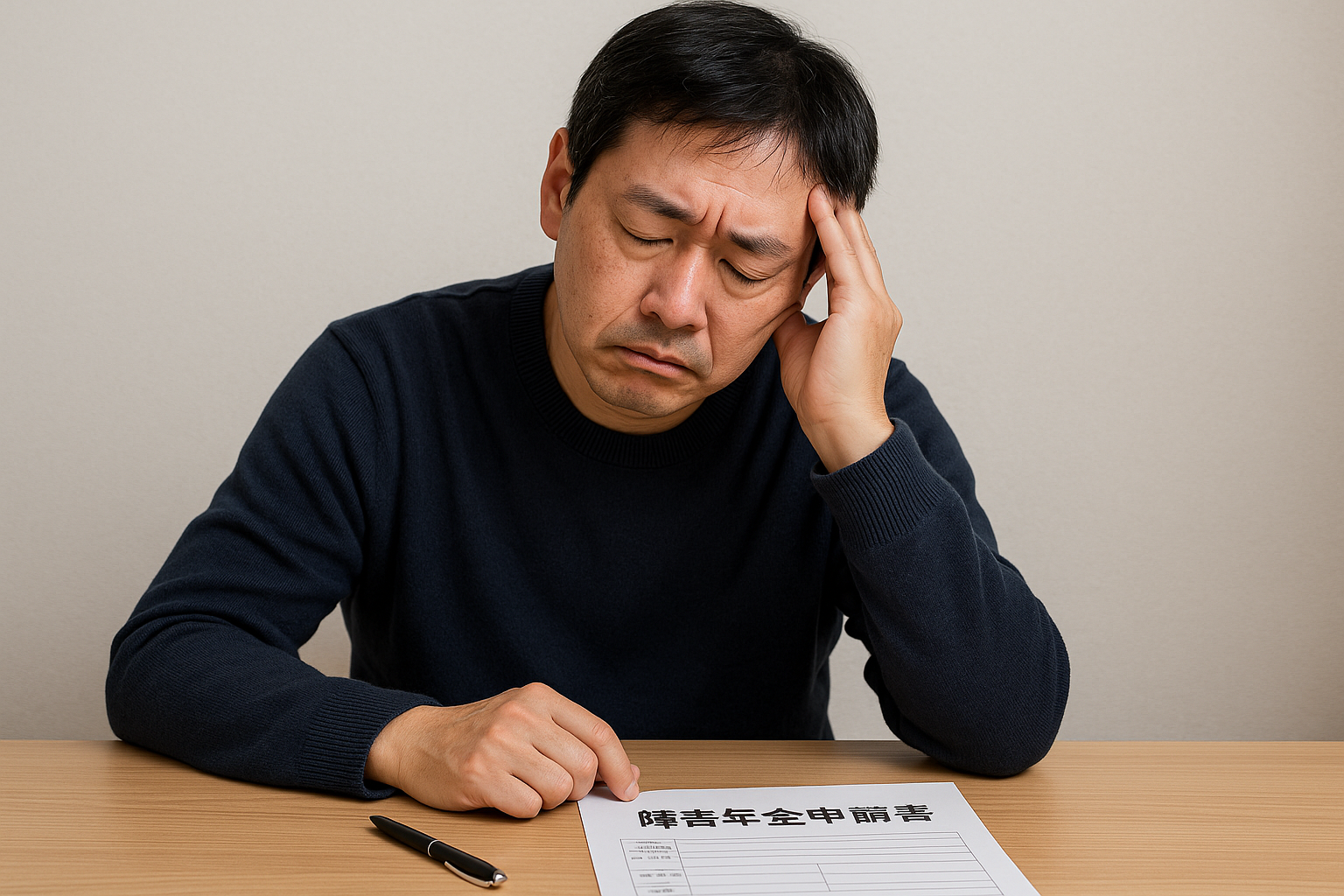
障害年金の申請は、病気で体調が安定しない中で、初診日を特定する記録を探したり、年金事務所で年金保険料済要件を確認したりと手続きが煩雑で専門的な知識が求められる場面が多くあり、大変なことです。
一方で、状況によっては自力で申請を進められるケースもあります。
本記事では「どんなケースなら自分で申請できるか」「どんな場合は社労士(社会保険労務士)に依頼したほうが良いか」について、具体的な判断基準を解説していきます。
自力で申請しやすいケース
以下に当てはまる場合は、ご自身で年金事務所や医療機関と連携しながら進めることも現実的です。
・年金納付状況が問題なく、納付済要件をすぐに確認できる
・初診日が1つの病院に特定でき、カルテや診療記録が残っている
・ 主治医が障害年金用の診断書作成に慣れており、協力的である
・ 申立書(病歴・就労状況等申立書)を自力で書ける、または家族の支援を受けて作成できる
・過去の遡及申請が必要ない、または遡及の必要性が明確でない
※障害年金の支給要件については、こちらの記事から
※初診日の特定については、こちらの記事から
※病歴・就労状況等申立書の書き方については、こちらの記事から
上記のような条件がそろっていれば、年金事務所の窓口や電話相談を活用しながら、自力で申請を完了させられる可能性が高いです。
しかし、実際には自力で手続きを試みたものの、初診日の特定が出来ない、年金保険料の納付要件を満たしていない等であきらめてしまったり、病歴・就労状況等申立書を書き始めたものの途中で行き詰ってしまう、というケースも少なくありません。
こういった場合は、どこで躓いているかを見極めて、そこだけを部分的に専門家に依頼するという方法もあります。
障害年金申請における社労士の位置づけ
障害年金の申請は、その申請者それぞれに特徴があり、誰一人として同じケースになることはありません。
なぜなら、病歴の推移は人それぞれであり、またカルテの保存期間(5年間)の関係で初診日の記録があったりなかったりという事が多分に大きなな要素を占めているからです。
また、これまで主治医とうまく関係を構築できなかったために、主治医が診断書作成をしぶったり、日常生活の困難さを的確にとらえた内容の診断書を書いてもらえない、ということもあるかもしれません。
こうした場合には、障害年金専門の社労士であれば、カルテ等の記録の捜索から、病歴・就労状況等申立書の作成援助やそれ以外の必要書類の添付や主治医に診断書を依頼する際の助言なども行います。
社労士に依頼したほうがいいケース
上記の事から、以下のいずれかに該当する場合は、社労士のサポートを受けたほうが、スムーズかつ有利に申請を進められる可能性が高いです。
🔸 年金納付状況が不安定で、納付要件を満たしているか自信がない場合
→ 納付漏れや免除期間などがあると、要件を満たすか微妙なケースが多くあります。そんな場合は専門家に確認してもらうのほうが手続きがスムーズです。
🔸 病院を複数転々としており、初診日が特定しづらい場合
→ 障害年金は「初診日」が極めて重要です。なぜなら、初診日に加入していた制度が国民年金か厚生年金かで年金額が大きく変わってくるからです。また誤った初診日で申請すると不支給になるリスクもあるため、その面でも社労士は証拠を収集しながら、正確な初診日の確定をお手伝います。
🔸 初診日当時のカルテや資料が残っていない場合
→ カルテが残っていないと初診日証明が困難ですが、社労士は「受診状況等証明書が添付できない申立書」や健康保険組合のレセプト等を使ったり、第三者証明などの方法で対応できるケースもあります。
🔸 病歴・就労状況等申立書の作成が難しい場合
→ 申立書は主治医が作成する診断書の内容に直結する重要書類です。そこでは、「病歴と治療内容」「就労状況」「症状」「日常生活状況」(別紙にまとめた方がベター)の点を、具体的かつ簡潔にまとめていくのですが、そこでは内容の一貫性や具体性が求められ、日頃から自分の症状や日常生活の状態を日記などにまとめておくなどしていないと作成はが困難になる場合が多いです。
🔸 主治医が障害年金用の診断書作成に不慣れな場合
→ ほんとどの医師は、障害年金についての的確な知識を持っていないのが実態です。というのは、医師になるための過程で障害年金について学ぶ機会がないからです。そのため、多くのケースで自己流で診断書を書いてしまい、必要な情報が漏れたり、障害の程度が適切に反映されないリスクがあります。障害年金専門の社労士は、その点を補って診断書依頼の仕方を助言し、場合によっては医師と連絡を取ってくれることもあります。
具体的な事例
◆体験談①:初診日不明で自力申請に行き詰まったAさんの場合
Aさん(40代・女性)はうつ病で10年以上前から複数の病院を転々としていました。
障害年金の申請を決意し、自力で書類を集めようとしたものの、初診日を証明できるカルテがどの病院にも残っていないことが判明しました。
年金事務所に相談しても「初診日を証明できないと申請できない」と言われ、途方に暮れていたところ、障害年金専門の社労士に相談。
カルテの代わりに診療明細や健康保険の受診履歴を活用し、さらに当時一緒に通院していた友人の「第三者証明書」を作成する提案を受けました。結果的に無事に初診日を確定でき、障害年金を受給できたそうです。
Aさんは「初診日が重要だとわかっていたけど、ここまで大変だとは思わなかった。自力では到底無理だった」と振り返っています。
◆体験談②:申立書作成で心が折れかけたBさんの場合
Bさん(30代・男性)は統合失調症で長期療養中。医師に障害年金を勧められ、自力で申立書を書き始めましたが、「どの程度まで詳しく書くべきか」「どこまで昔のことを思い出して書くべきか」が分からず、書いては消しての繰り返しで心が折れかけました。
最終的に障害年金専門の社労士に依頼し、ヒアリングを受けながら申立書を一緒に作成。
客観的に生活状況を整理してもらえたことで、自分の症状や困りごとを的確に伝えられる内容になり、無事に年金を受給できました。
Bさんは「自分では整理できなかったことを第三者の視点でまとめてもらえて心強かった」と語っています。
社労士選びのポイント
開業社労士の約9割が、中小企業と顧問契約を結び、労働社会保険関連書類の作成代行などの人事労務管理を主なサービスとしていますが、ここ昨今では自分の様な精神疾患を主に扱う障害年金専門の社労士も増えてきました。そこで、どのような観点から、社労士を選んだらいいかについて下記の通りまとめてみました。
①相性があうかあわないか
障害年金の申請業務は、年金機構の審査期間の関係で、始めてから申請、入金されるまで半年以上はかかり、かつ不服申し立てまで進むと1年以上はかかります。その期間、様々なやり取りを行うのですから、相性は重要な要素です。したがって、まずは電話やオンライン無料相談などで相談してみて、ご自身の問題解決に全力で対応してくれそうかどうかという観点から判断すべきです。
②自宅から近い人で決める
障害年金の申請書類作成は、オンラインでのやり取りでは不十分な面があり、リアル対面でもコミュニケーションが不可欠であると考えます。また、主治医へのフォローも、遠く離れた場所に拠点がある社労士だと難しい事も想定されるため、やはり家から近場に拠点を構える社労士を選ぶのがベターです。
③不服申し立て(審査請求)に対応しているか
障害年金の申請は、その道の専門家が行っても一定数の不本意な決定がでることはどうしても避けられません。当該決定にの場合に、不服申し立ての対応をしていない社労士だと、そこで申請を断念せざるを得なくなってしまいますので、途中であきらめてしまうことなく、不服申し立てまで対応可能な社労士に依頼することも大事です。
④精神疾患専門であるかどうか
ここ昨今のメンタルヘルス問題から、精神疾患専門の社労士も増えてきていますが、これはいいことだと思います。それは、精神疾患には特有の書類作成ガイドラインと特定の診断書フォーマットがあり、多岐の病気の対応していると、精通する必要のある守備範囲も膨大になってしまうので、精神疾患特有の細かい話までついていけない事があります。ですから、うつ病等で申請する場合は、精神疾患専門という観点から選ぶべきだと考えます。
⑤実績を重視する
障害年金の申請の特徴は、一発勝負という面が大きく、不服申し立ての制度があるとはいえ最初の決定を覆すことは容易ではありません。特に精神疾患の場合は目に見えない病気であるため、症状の状態や経緯なども千差万別です。従って、様々な申請経験がないと、適切な書類作成につながりません。
個人的な目安としては、精神疾患の場合、精神科医療や病気の種類、薬剤の知識まで必要となってきますので、最低でも60~70件の申請経験が必要だと考えます。
総合的な考察
社労士に依頼する場合、初期相談は無料のところが多く、成功報酬型で受給決定後に支払う仕組み(報酬相場は年金2~3ヶ月分程度)です。
専門家の知見を活用することで、不支給リスクを下げ、より適正な年金額を受給できる可能性が高まるという見方はできると思いますが、中には「主治医には会えない事になっている」などと言い訳がましい事をいって、遠回しに依頼を断る社労士もいますので、まずは初回無料相談を活用して、最後まで丁寧に対応してくれるかどうかなどの相性をよく判断すべきです。
また障害年金の申請は、上記に述べたように自力でできるケースもあれば、初診日証明や診断書作成、申立書作成など、複雑な要素が絡むケースが多々あります。
自分の状況を冷静に整理し、少しでも不安がある場合は、まずは初回無料相談などを活用し、専門家の知見を活用して先々の大まかな見立てだけでも立てておくことをおすすめします。
そのうえで、自力で申請できそうな見通しがたてば、余計な費用はかけずに自力で行う事も不可能ではありません。
※自力で申請を行う場合の、ポイントなどを解説した記事はこちらから。
いずれにしても、障害年金の受給は生活を支える大切な権利です。
不支給決定の通知が出てしまってからでは遅いので、先々を見越して後悔ないよう、自分の置かれた状況を客観的に見つめなおし、自力では対応できない部分(初診日の特定や病歴・就労状況等申立書の作成等)は専門家を活用するなど、適切な方法で申請を進めていきましょう。
◆トップページ・運営者プロフィールはこちらから。