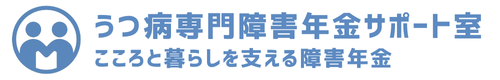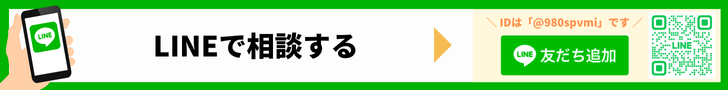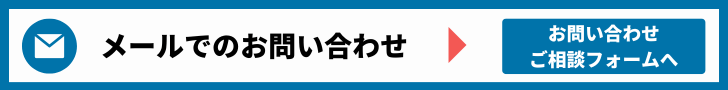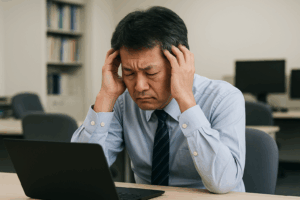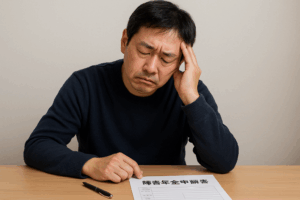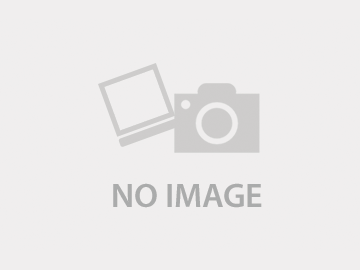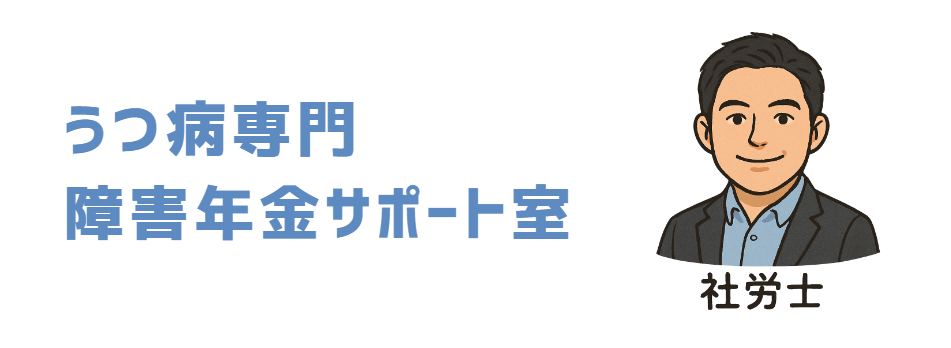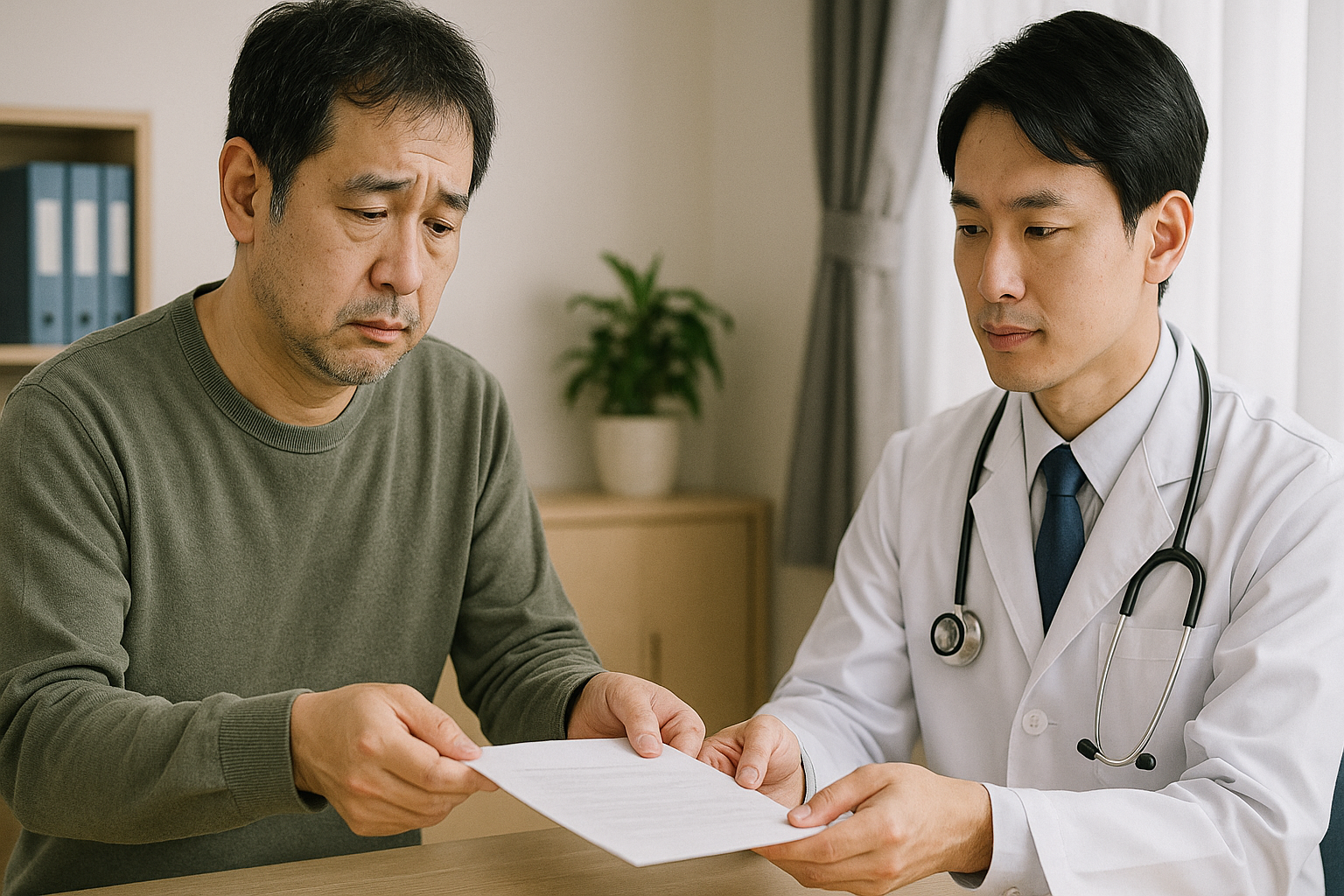
障害の状態を検査数値などで示すことが出来ない精神疾患の場合、「どのように生活に支障が出ているのか」「その支障が就労にどう影響しているのか」を正確かつ具体的に主治医に伝えることは、認定審査で一番重視される診断書作成の質を左右する極めて重要なポイントです。
そのため、通常の「病歴・就労状況等申立書」とは別に、以下の7項目に関して詳細に記載する「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」書式を活用することを強く推奨します。
※病歴・就労状況等申立書の書き方については、こちらから
本来当書式は、申立書とは別に、審査の段階で、認定医より必要と判断された場合に、提出を求められるものです。しかし、それよりもむしろ年金請求の際に、あらかじめ準備しておくことで、申立書とあわせて当書式を活用することで、日常生活や就労状況を主治医や認定医にしっかりと伝えられることが出来るため、うまく活用すべきなのです。
適切な食事
ここの項目では、食事のとり方や、調理・配膳・片付け、計画的に献立がたてられるか、や自分で適切の調達できるかといった観点から記載していきます。
具体的には、下記のような記載です。
現状:朝は起きられず食事を摂らないことが多い。食事の準備や買い物に出る気力もなく、夕食はコンビニ弁当や菓子パンなどで済ませている。
援助:毎日、母が食事を作って持ってきてくれる。自分ではほとんど調理できない。
就労への影響:エネルギー不足や血糖の乱れで集中力が出ず、勤務に支障がでている。朝食が摂れないと通勤も難しくなる。
上記のように、援助者(母)が作った食事を自室に運んでもらい、当事者が食べたい時だけ、1日1食だけ食べていた場合でも、捉え方によっては、診断書の「適切な食事」欄の判定は「できる」となってしまいます。
ですから、上記のように実態を、具体的事実も盛り込みながらまとめて主治医に伝え、日常生活状況を総合的に判断してもらうことが必要です。
身辺の清潔保持
この項目は、入浴・洗面・歯磨き・髭剃り・整髪などの身だしなみや、トイレの使用、衣服の選択が寒暖による調節ができるか、自室の掃除や片付けが出来るかといったことが問われます。
具体的な記載例は下記のとおりです。
現状:数日間、入浴や歯磨きができないことが多く、洗濯も溜めてしまう。部屋の掃除もほとんどできない。
援助:家族が頻繁に訪問し、洗濯や清掃を代行している。
就労への影響:外見を整えることが難しく、職場に出るのが恥ずかしい。朝の支度に時間がかかり遅刻しやすい。
ここで注意すべき点は、診断書を作成する主治医は、通常、当事者の身だしなみを整えた状態しか見ていないことが多いことです。
通院する時は、援助者が、外出して他人から見られても恥ずかしくないように、または気温や天候なども考慮して、服装を決めています。
つまり、主治医は、本当の当事者の実態を知らない事が通常なのです。
したがって、診断書の作成を依頼する際は、上記のように「日常」の実態について詳細に伝える必要があります。
金銭管理と買い物
この項目では、①正しい金銭管理:給与の管理や1月単位での生計費の管理ができるか②買い物:必要な商品を判断して買い物ができるか、予算の範囲内で計算して買い物ができるか③浪費癖がないか、といったことが問われます。
具体的な記載例は、下記のとおりです。
現状:必要な支払い(家賃・携帯代など)を忘れることがある。買い物に行っても何を買うべきか判断できない。
援助:実家の母が金銭を管理。買い物も同行や代行をお願いしている。
就労への影響:給与管理や通勤費の計算・提出ができず、サポートがないと手続きできない。
上記のように、当事者だけで所持金額を正しく把握して、本当に必要なものだけを適正な価格で必要な量だけ購入できなかったり、先々の収支も考えた買い物をすることができずに、浪費してしまう、という場合は、その事をきちんと主治医に伝わるように書いていくことが重要です。
通院と服薬
この項目では、①通院:通院の必要性の理解や自身の病状を正しく主治医に伝えられるか、主治医の助言を理解し守れるか②服薬:服薬時間や服薬量を守れるか、飲み間違いなどの危険がないか、といったことが問われます。
具体的な記載例は下記のとおりです。
現状:病院の予約を忘れることが多い。薬の飲み忘れや、気分が落ち込んだ時に過剰に服用してしまうこともある。
援助:服薬スケジュールは家族が管理し、LINEで毎日服薬を促してくれている。通院時は送迎も行う。
就労への影響:服薬が安定しないと体調の波が大きく、就労が継続できない。
上記には記載していませんが、自分の病状を正しく主治医に伝えられるかも大きなポイントです。
それができないのであれば、「自分の状態を医師に伝えることや、医師の話を聞き理解することが難しいため、家族の付き添いが必要である」と記載し、自力での通院が困難であることをアピールします。
他人との意思伝達及び対人関係
この項目では、①会話:自分の意思などを相手に上手く伝えられるか、相手の話を聞いて理解できるか②対人関係:相手との距離感や相手の気持ちの理解や配慮③集団的行動:組織のルールを理解し守れるか、場にそぐわない言動がないか、といったことが問われます。
具体的な記載例は下記のとおりです。
現状:人との会話に強い緊張を感じる。知らない人に話しかけられるとパニックになり、返答できないこともある。
援助:役所や医療機関では家族や支援者が代弁している。
就労への影響:電話応対やチームでの作業は極度のストレスになる。報連相ができず、業務に支障が出ている。
基本的な双方向のコミュニケーションがとれるかどうかがポイントなのですが、上記のようにそれが出来ない状況であれな、そのことを具体的に記載します。
また、就労との関係でいえば、組織の中で自分の位置づけを理解し、他の社員と一緒に行動できるかどうかが判断基準になるのですが、うつ病等の場合はそれが一番難しい局面でもありますので、この項目は低い評価になる傾向があります。
身辺の安全保持及び危機対応
この項目では、①電車などの公共交通機関の利用:安全に利用できるか②危険性の理解:周囲に注意を払いながら歩行できるかやその危険回避、といったことが問われます。
具体的な記載例は下記のとおりです。
現状:死にたい気持ちが強まることがあり、自室に引きこもってしまう。火の消し忘れ、ドアの鍵の締め忘れも多い。
援助:週1回訪問看護を利用している。また家族が定期的に様子を見にいっている。
就労への影響:一人での通勤中に体調が急変する恐れがあり、常に不安があるため働くことに大きな支障がある。
上記のように、希死念慮が強い場合などは、通常とは異なる危険が目前に迫ったときにパニックになりがちですし、特に車の運転などはとてもできる状態ではありません。
もし車の運転で交通事故をおこしてしまった場合の、被害者との折衝ができるかという点も評価されるのですが、うつ状態ではそれも困難だと考えられます。
そういった仮のケースも考慮しながら、具体的に記載し、病状をアピールしていくと有効です。
社会性
この項目では、①手続き等:社会生活に必要な事柄や基本的なルールの理解、行政機関や銀行等の利用が適正に行えるか②公共機関の利用:公共交通機関や公共施設の利用が適正にできるかやルールを守れるか、といったことが問われます。
具体的には、下記の通りの記載になります。
現状:公共交通機関で強い不安が出る。人が多い場所や音が大きい場所ではパニックを起こすこともある。役所などの手続きも一人では対応できない。
援助:移動はタクシーや家族が送迎を行う。行政機関での手続きは支援者が同行している。
就労への影響:通勤や社会的な業務(接客、営業など)が困難で、対外的なやりとりが精神的に大きな負担となる。
上記のような社会性の有無は、日常生活を送る上で重要な事項なのですが、行政機関での手続きなどを行う場合、「わからない事は聞いて確認する」といったコミュニケーション能力も必要となるため、うつ状態にある方にとってはハードルが高いところでもあります。
最後に:主治医への情報提供は「診断書の精度」を決定づける
診断書は、障害年金の審査において最も重視される資料です。主治医に対しては、口頭だけでなく、病歴・就労状況等申立書や「日常生活及び就労に関する状況に関する状況について」を活用して書面で日常生活の実態を伝えることが非常に重要です。
この書式は、あくまでも本人・支援者から医師に向けた補足情報という位置づけではありますが、主治医の判断を助け、正確な診断書作成を促すものです。
可能であれば、できるだけ支援者(家族、福祉関係者など)と一緒に作成することで、より客観性と説得力が増しますし、と同時に主治医に日常生活の困難さを客観的に伝える強力な材料となりえるのです。
◆トップページ・運営者プロフィールはこちらから