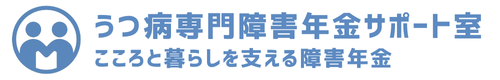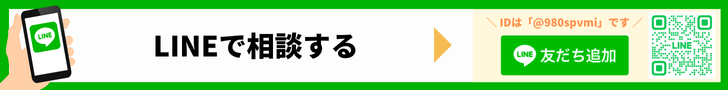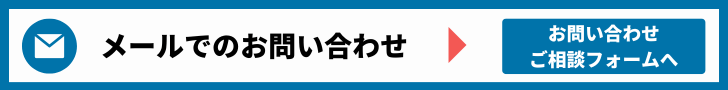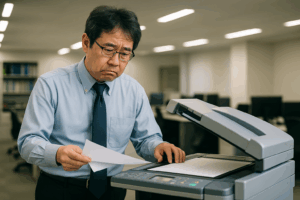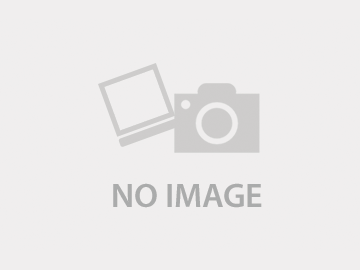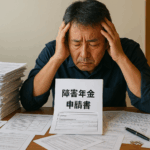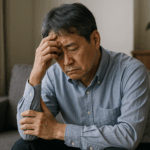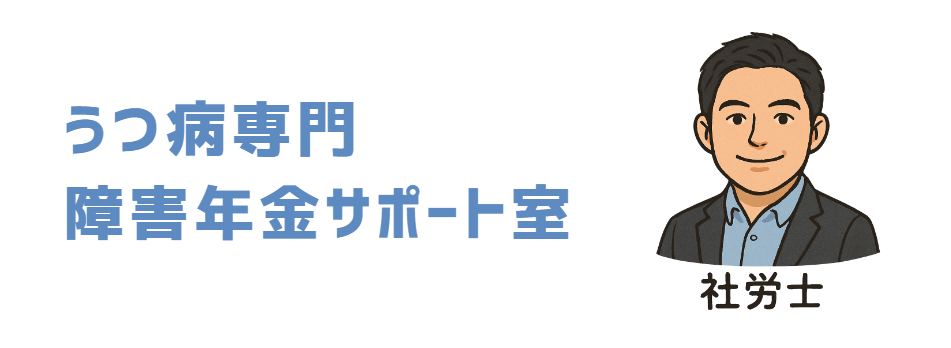高年齢者雇用安定法の規定
従前の高齢法では、60歳から65歳までの再雇用について労使協定で条件を設定することが認められていまいした。具体的には、再雇用の対象者について、健康状態や勤務成績などにより一ものを除外するような協定を結ぶケースが多かったと思われますが、法の趣旨としては、この様なケースはあくまで例外的に除外するための基準であり、基本的には再雇用するのが望ましい、というものです。
そこで、平成24年の高齢法改正によって、60歳から65歳までの継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止され、定年を65歳未満に定めている会社は、年金支給開始年齢の引き上げに対応するために、高年齢者雇用確保措置として、
・65歳までの定年の引き上げ
・継続雇用制度(再雇用制度もしくは勤務延長制度)の導入
・定年制の廃止
のいずれかの措置が義務付けられました。
そして、平成25年3月31日までに労使協定により制度適用対象者を定めていた場合は、その基準を適用できる年齢を令和7年3月31日までに段階的に引き上げなければならいないものとされました。
つまり、会社の経営状態と照らし合わせて運用しやすい面から、再雇用制度を選択するケースが多いと想定されますが、その場合は、原則として希望者全員を対象とする必要があります。
対象者基準についての経過措置
改正法の施行までに、改正前の高齢法に基づき、有効な再雇用制度の対象者基準に関する労使協定を締結している会社においては、令和7年3月31日までの間、再雇用の対象者にかかる基準を厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢以上の労働者を対象に、利用することが出来ることとされています。
この経過措置は再雇用制度の対象者を限定する基準を定めることを認めるものですが、再雇用の基準は、労働者にとっては60歳以降の雇用が確保されるかどうかの重要な判断基準です。ですので、その基準に基づく選別は、経営者の一方的な判断によることはできず、労働者の過半数代表者との間の協定でその基準を定め、その基準のそって選別が行われる場合に限り認められます。
当該基準を定めるにあたっては、職場の実態を経営者・代表労働者ともに熟知しているはずで、その判断基準をきちんと労使協定で定める基準に反映させるべきです。
再雇用制度の規律
高齢法に基づく「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」によれば、再雇用制度では希望者全員を対象とするのが原則です。
しかし、当該指針では合わせて、「心身の故障のために業務に堪えられないと認めれること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たしえない事など、就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢にかかるものを除く)に該当する場合には、継続雇用しないことができる」とされています。
そこで、例えば、簡易的な体力測定を行う事によって、「心身の故障のために業務に堪えなれない」と判断できる程度の客観的な事実があれば、退職事由に該当すると考えられるケースもあります。
しかし、簡易的な体力測定で会社が恣意的に設けた基準に達しない者の再雇用を簡単に拒否できるようでは、指針の示す原則希望者全員の雇用の趣旨に反します。
また、同指針では、就業規則に定める解雇事由または退職事由と同一の事由を、再雇用しないことができる事由として就業規則に定めることができ、再雇用制度の円滑な実施のため労使が協定を締結することができる、ともありますが、それらによって解雇事由又は退職事由とは異なる運用基準を設けることは、高齢法の趣旨に反する恐れがあります。そのため、再雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められるという、労契法の定める雇止めの法理や解雇権濫用の法理と同等の理由がなければ、再雇用の拒否は難しいといえます。
過去の判例から読み解く
最高裁では、定年後引き続き1年間の嘱託雇用契約により雇用されていた労働者が、会社の高年齢継続雇用規定に基づいて嘱託雇用契約終了後の継続雇用を希望したが、会社が再雇用契約を締結しないことを通知したため、雇用契約上の地位確認などの請求を求めた事案について、
・当該労働者は同規定所定の継続雇用基準を満たすものであったから、当該労働者の「嘱託雇用契約の終了後も雇用が継続されるものと期待することは合理的な理由があると認められる」とし
・同規定に基づく再雇用をすることなく嘱託雇用契約の終期の到来により、当該労働者の雇用が終了したものとすることは「客観的合理的な理由をかき、社会通念上相当であると認められない」と判示し、
労契法に定める雇止め法理(解雇権濫用法理)を適用することを明らかにしました。
このことから読み取れるのは、いったんは再雇用されたものの、例えばそれが上記事例にように1年契約のような場合、65歳に達する以前に雇止めされる場合にどうなるかということです。
この様な場合にも、経営者には65歳までの雇用が義務付けられているので、雇用継続に対する合理的期待は原則として認められ、雇止めとなった場合には、その雇止めに合理性・相当性があるか否かの観点から雇止めの有効性が判断されると考えていいでしょう。
再雇用後の労働条件(参考)
厚労省によれば、高齢法が求めているのは継続雇用制度等の導入であり、経営者に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、会社が合理的な裁量の範囲内の労働条件を提示していれば、たとえ労働者と経営者の間で労働条件などについて合意が得られず、結果として再雇用ができないとしても、違法にはならないと考えられています。
したがって、定年後再雇用した労働者に対し、定年前とは異なる業務内容で契約することも、また、その業務内容に応じて賃金を引き下げることも合理的な範囲内であれば、可能となることに注意が必要です。
※定年後再雇用で賃金が下がった場合には、一定の要件を満たせば、雇用保険より高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。
しかし、どのような業務内容の変更も許されるわけではありません。
過去の判例で、トヨタ自動車ほか事件があります。
この事案においては、定年前にホワイトカラーとして事務職に従事していた労働者に対して、会社が定年後再雇用後の業務として、シュレッダー機のゴミ袋交換及び清掃などを提示しました。
裁判所は、定年前の業務と定年後の業務が、「まったく別個の職種に属するなど性質の異なったものである場合には、もはや継続雇用の実質を欠いており、むしろ通常解雇と新規採用の複合行為というほかないから、従前の職務全般について適格性を欠くなど通常解雇を相当とする事情がない限り、そのような業務内容を提示することは許されない」として違法と判示しています。
高齢法の求めるところ
高齢法が定める高年齢者雇用確保措置は、定年制自体は許容する一方でこれにより労働者がもつ労働への意志や能力の有無にかかわらず労働市場の場から退出する年齢を65歳以上に限ることで、高齢者の職業安定等の向上を図り、社会経済の発展に寄与することを目的としています。
つまり、当該労働者が懲戒解雇の該当するような問題を起こしたという場合を除いて他に問題がなければ定年で雇用を自動的に終了させることなく、希望者全員を65歳まで雇用する制度の導入を求めているのです。
ですから、業務遂行能力等に多少の難があるという程度で再雇用制度から除外するという事は出来ません。
仮に勤務成績が不良で、それが就業規則の解雇事由に該当するのであれば別ですが、そこまでの勤務成績不良でなければ再雇用制度の対象に乗せる必要があります。会社としては解雇はしたいが、解雇権を行使すればそれが濫用とみなされ無効となる恐れがあるからというだけで、当該労働者を再雇用制度の対象にしないということはできないのです。
◆トップページ・運営者プロフィールはこちらから