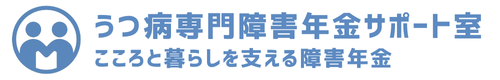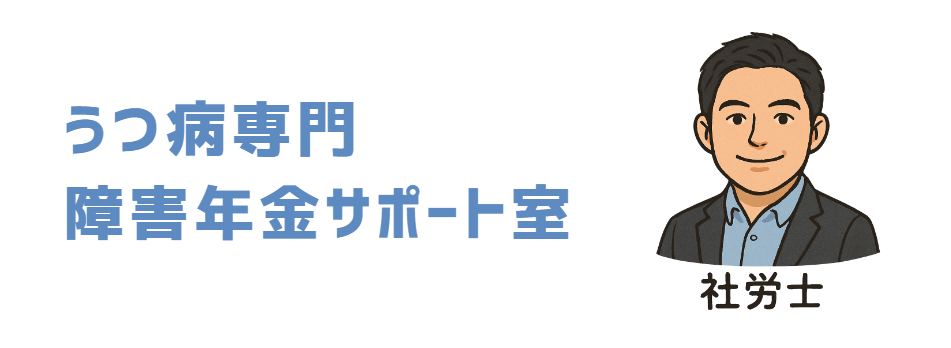「誰ひとり取り残さない」ために
支援機関の皆様とともに取り組む、うつ病による就労困難者への障害年金支援
はじめまして。私は、うつ病や職場のメンタル不調により就労が困難となった方々の障害年金申請とその後のライフプランニングを専門にサポートしている社会保険労務士です。
本稿では、地域の最前線で生活・就労支援を担っておられる皆様へ、私の支援スタンスと、連携によって被支援者の皆様に提供できる価値についてお伝えさせていただきます。
◆ 支援の現場で見えてくる「制度の壁」と「申請の壁」
生活困窮者自立支援窓口や社協、障害者就業生活支援センターなど、貴機関には、職場うつやメンタル疾患により働けなくなった中高年男性の方々が数多く相談に訪れているかと存じます。
しかし、多くのケースで見られるのが、
-
既に退職しており、毎月の収入がない
-
働ける見込みが立たず就労支援にもつながらない
-
心療内科など医療機関との関係性も希薄
-
生活保護申請も心理的ハードルが高く、ご本人が拒否している
といった、「制度の狭間」で身動きが取れなくなっている状況にあるかと思います。
本来であれば、うつ病等による長期の就労困難な状態は、障害年金の対象となり得るにもかかわらず、
-
障害年金の制度そのものを知らない
-
申請書類作成の難易度が高い
-
年金事務所の形式的な対応で、門前払いをされた経験がある
- うつ病等の精神疾患では障害年金を受給できないという誤解
といった理由から、多くの方が申請に至っていないのが現状です。
仮に制度を知っていて自分で申請を行おうと思っても、うつ病等の精神疾患にある方々の場合は、特にその障害の性質上、請求に困難が伴います。
うつ病の場合は、日中は気分が沈みがちで何かをやろうとする気力や意欲も乏しいですから、障害年金の複雑な書類作成をやり遂げるのは、かなり困難だといえます。
◆ 「一緒に申請を乗り越える」専門家として伴走します
私は、こうした「支援の手が届かない」ケースを減らしたいという思いから、障害年金の専門家として、うつ病等のメンタル疾患と向き合う方々への申請支援を行っています。
特に以下のようなケースでは、支援機関の皆様と連携することで、より丁寧で現実的な支援が可能になります
-
初診日が曖昧で、病歴が複雑な場合(通院中断や病院の廃院等を含む)
-
生活状況が不安定で、必要書類の準備が進まない場合
-
病識が薄く、申請に抵抗を示す場合
特にうつ病等の場合は、長期の治療が必要になることが多く、それに伴う転医も多いことから初診日の証明に非常に苦労することがよくあります。
初診日を証明する医証のもととなるカルテは、「受診終了後5年間」の保存が義務付けられていますが、これは逆を返せば、5年を過ぎたカルテはの保存義務はなく、破棄してしまう医療機関もあるということです。
一方、障害年金の申請書類の初診証明の期間に限度はなく、初診が5年よりずっと前の事でも、医証の提出を求められます。
この点が、障害年金の申請の難易度を高めている原因の一つともいえますが、医証による証明が出来ない場合でも、例えば健康保険組合の給付記録(レセプト含む)や電子カルテなどの記録から、初診日の証明をあきらめることなく目指します。
また私は、本人の理解度や体調に応じた面談ペースを大切にし、必要に応じて、職員の方やご家族と三者面談を通じて信頼形成を行います。診断書の記載内容にも丁寧にアプローチし、主治医との橋渡しも行うよう努めております。
◆ 提携のメリット:支援機関様・ご本人双方にとっての「安心と前進」
支援機関の皆様にとって、私との連携によって得られる具体的なメリットは以下の通りです
● 被支援者様に対して
-
社会保障制度の専門家として「毎月の収入がない」状態から脱却する手段を提示できます
-
自身が数々の職種を経験してきたことから、自立支援プランに現実的な展望を加えることができます
-
自立支援プランを通じて、ご本人の「社会的自己評価の回復」につなげます
障害年金が受給できれば、最低限の経済的な安定も得られるようになり、気持ちも社会復帰に向けて前向きになっていきます。
その中で、まずは無理のない身の丈に合った働き方から始めて、少しづつステップアップしながら社会復帰を目指すことも可能です。
● 支援機関様に対して
-
職員の皆様が、障害年金の細かい制度や運用を把握していなくても、安心して専門家に委ねられる体制を構築できます
-
ケース検討会などでの情報共有により、多機関連携がしやすくなります
-
「申請代行業務」は行わずとも、「制度活用支援」を提供できる体制を示すことで、支援機関としての信頼性や支援範囲が拡大します
特に多機関連携については、たとえば、生活支援員・就労支援員・医療機関・ケースワーカーなどが関わる支援会議(ケース会議)に、障害年金専門の社労士も参加・情報提供を行うことで、支援の全体像が共有されやすくなります。
この情報共有により、申請手続きの進捗、主治医への診断書依頼の内容、病歴・就労状況等申立書の方向性などを共有することで、他職種との連携(就労支援・医療支援)がズレなく連動しやすくなります。
その結果、被支援者様への対応が「点」ではなく「線」となり、より統合的で効果的な支援が可能になります。
◆ ともに地域の「セーフティネット」を強くするために
うつ病による離職・就労困難という課題は、今後さらに増加が予想されます。特に中高年男性においては、「助けを求める言語を持たない」まま、生活困窮へと転落していくケースが後を絶ちません。
そうなると、ご本人が、ご家族とのコミュニケーションも希薄になっていく事も多く、ご家庭が離婚などで崩壊してしまうといった悲劇が生まれてしまう事も十分に想定されます。
私たち専門職が連携し、支援機関の皆様と力を合わせることで、「制度の谷間」に落ちかけた人々にもう一度立ち上がる機会を提供することができると信じています。
障害年金の申請支援や受給後のライフプランニングを通じて、貴機関の支援対象者様にとって、「生活再建の一歩」となる支援を共に届けていければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。